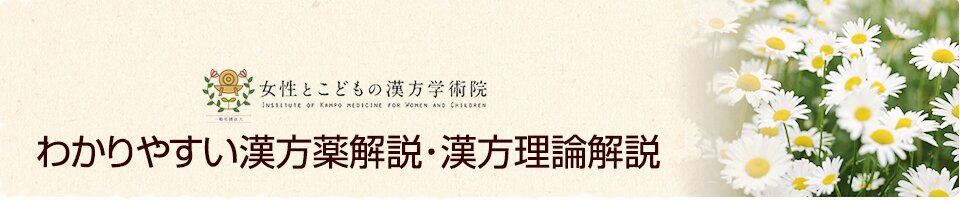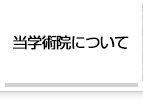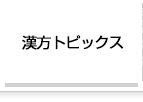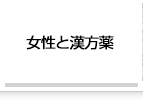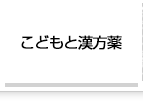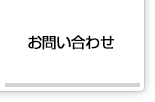私たち(一般社団法人)女性とこどもの漢方学術院は漢方薬を通じて女性とこども達の健康を支えます。 | 女性とこどもの漢方学術院
なぜ今、漢方なのか
近年、漢方に注目が集まっています。大型のドラッグストアには数多くの漢方薬が並び、雑誌にもしばしば漢方特集が組まれています。なぜこのような潮流が生まれたのかを考えると二つの側面が見えてきます。
ひとつは漢方薬の有効性が科学的(統計学的)に再評価されたことが挙げられます。漢方薬の効果に対して客観的な分析が進み、その力が広く知られるようになりました。そしてもうひとつは西洋医学的な治療とは異なる選択肢として、漢方が選ばれているという側面もあるでしょう。
西洋医学は人類が生み出した最も素晴らしい技術であることに疑いはないでしょう。特に古代から人類の敵であった感染症に対して公衆衛生の改善とともに西洋医学は多大な貢献をしてきました。さらに西洋医学的な手術に比肩する外科的治療法をもつ他の医学は存在しません。その一方で今日、西洋医学的アプローチでは対応が困難な問題も浮上しています。
西洋医学は病気を起こす特定の存在が明らかな場合、それを鋭く攻撃することを基本的な戦略として絶大な力を発揮します。例えば抗生物質は細菌を、抗ウイルス薬はウイルスを倒すことによって感染症を治療します。鎮痛剤の成分として有名なアスピリン(一般名はアセチルサリチル酸)は痛みを起こす「物質」を体内で作りにくくすることで効果を発揮します。しかしながら、そのような存在が見つからなかった場合などは西洋医学的なアプローチは困難に直面してしまいます。
一方の漢方医学は病気や体調不良に対してのアプローチが異なります。漢方医学では身体内における気(き)・血(けつ)・津液(しんえき)や五臓六腑(ごぞうろっぷ)などのバランスを重要視します。何らかの存在によって上記のバランスが崩れてしまった状態を漢方医学では病気の状態と捉え、漢方薬はこの崩れたバランスを回復することで治療を行います。
したがって、西洋医学的な病原的存在が確定しなくても治療を行うことが可能なのです。換言すれば漢方医学は西洋医学的な視座からは病気と判断できない、または判断しないような症状にも対応してゆくことができるのです。
私たち日本人が生きる現代はとても便利な時代です。ほぼすべての人が西洋医学的な治療にアクセスすることができる時代でもあります。しかしながら、博報堂生活総研が1990年代から行っている大規模調査(生活定点1992-2014)において一貫して約60%は「健康に不安がある」と答えています。このような背景の中で、漢方医学は西洋医学では対応が難しい健康問題に対しての、異なった視点からの解決策として再評価されていると考えられるのです。
繰り返しになりますが、西洋医学が人類の健康に多大な貢献をしてきたことは事実です。21世紀に入り再生医療というまったく新しい治療法も生まれ、日々進歩を続けています。今後、西洋医学界では私たちが想像もできないような治療技術のブレークスルーも起こり続けるでしょう。
しかし、ヒトの心身はある一面を見ただけですべてが把握できるほど平面的なものではないはずです。より複雑で立体的な存在であるヒトを見るためには異なった視点も不可欠です。今後、西洋医学だけでは対応が難しい健康問題を漢方医学などが補完してゆくことが、望ましい医療の姿なのではないでしょうか。
【わかりやすい漢方薬解説・漢方理論解説】では漢方医学の概説、基礎理論やより実践的な治療法、そして具体的な漢方薬や生薬のはたらきなどを紹介してゆきます。漢方の知識が無い方でも読み進められるように構成されておりますので是非、漢方を知るための「入口」としてご活用ください。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
「漢方薬」の定義とは
みなさんは「漢方薬」という言葉からどのようなイメージが浮かびますか。漢方薬をかの有名な広辞苑で調べてみると「漢方で用いる薬。おもに草根・木皮の類。」という答えでした。この定義は決して間違っていませんが、充分ともいえないでしょう。
漢方薬は一部の例外を除けば2種類以上の生薬を組み合わせて作られています。この生薬とは広辞苑が示した通り、植物の根や皮などが中心となります。それ以外にも実、種、葉なども使用されます。植物以外にも大型哺乳類(サイ、ゾウ、シカ、マンモスなど)の化石である竜骨や鹿の角である鹿茸など動物由来の生薬も多く存在します。
上記以外にも生薬にはヤマイモ(生薬名は山薬)、シナモン(生薬名は桂皮)、ミカン(使用するのは皮の部分で生薬名は陳皮)、薄荷、小麦、粳米、胡麻、紫蘇、山椒など食品やスパイスとして幅広く用いられているものも少なくありません。
ここで再び生薬から漢方薬に話は戻ります。恐らく日本で最も有名な漢方薬である葛根湯も葛根や麻黄といった7種類の生薬から成り立っています。この葛根湯は紀元後200年頃に書かれた傷寒論(しょうかんろん)という本に収載されています。
このように漢方薬と定義されるには一定の評価を得ている文献に、どのような生薬たちがどれくらいの量を必要とするのかなど記載されている必要もあります。 したがって、健康茶として歴史の深いドクダミやセンブリは上記の定義と鑑みて漢方薬とはいえません。サプリメントの成分として有名なマカやブルーベリーなども同様です。
さらに「どうき・息切れ・気つけに」のフレーズで有名な「救心」やラッパのマークで有名な「正露丸」は明治時代など近代に日本の製薬会社が生んだ薬であり、やはり漢方薬ではありません。これらはしばしば伝統薬や家伝薬などと呼ばれます。
逆にドラッグストアで売られているカコナールシリーズ(第一三共ヘルスケア)は葛根湯、ナイシトールシリーズ(小林製薬)は防風通聖散という漢方薬です。これらは恐らく製薬会社側が漢方薬本来の名前では他社製品と差別化ができないといった理由でカタカナの商品名にしたのかもしれません。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学の歴史 (1)
ここからは漢方医学の歴史を辿ることで、そもそも漢方医学とはどのような医学であるのかを見てゆきたいと思います。日本における漢方の歴史はその背景的な違いから大きく前後2つに分けることができます。
まず前編は中国からの「輸入」に大きく頼っていた、冊封体制(中国中心の国際秩序体制)の時代です。そして後編は輸入してきた中国伝統医学を日本人に合う形へと改変していった時代、日本独自の医学である漢方医学が生まれ、そして現代へ至る時代です。
まず中国伝統医学の歴史はとても深く、その原型となる理論などは少なくとも紀元前1000~700年くらい昔までさかのぼることができるといわれています。文字通り「中国3000年の歴史」ということですね。
時間は進み紀元前200年頃、中国伝統医学からみた人体の構造や病気の仕組み、鍼灸を用いた治療法や健康法を記した黄帝内経(こうていだいけい)が成立しています。ちなみにこの黄帝内経(素問と霊枢という二部構成になっている書物です)が中国最古の医学書といわれています。
さらに紀元後200年頃には植物薬・鉱物薬・動物薬などの薬効を記録した神農本草経(しんのうほんぞうきょう)も書かれています。神農本草経はこれらの薬を上薬・中薬・下薬にカテゴライズしたことでも有名であり、中国最古の薬物辞典といわれています。
そして同じ頃の後漢の時代には張仲景が著したとされる傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)が生まれます。傷寒雑病論は後に「感染症対策マニュアル」のような存在である傷寒論(しょうかんろん)と慢性病を扱った金匱要略(きんきようりゃく)に分離独立します。
このように紀元前と紀元後をまたぐ数百年の間に中国では植物や鉱物を用いた薬物治療、それに加えて鍼灸治療も行われていたことがわかります。傷寒論と金匱要略が成立した頃の日本は弥生時代の後期、邪馬台国の卑弥呼が争いを鎮めて、紀元後239年に中国(当時は魏)から親魏倭王の称号と金印を授かったとされています。
日本が小国同士の戦いに明け暮れていた時代に中国では感染症に対する薬物治療が行われていたことになり、当時の中国がいかに「先進国」だったかがわかります。
中国伝統医学が日本に伝わってきたのは紀元後400年頃のヤマト政権の時代です。多くの渡来人が来日して進んだ大陸の鉄器や土器の製造技術が流入してきた時代でもあります。その頃、倭の五王の一人とされる允恭(いんぎょう)天皇が来日した医師から中国伝統医学を用いた治療を施されてという記録があります。
600年頃からは聖徳太子が指揮した遣隋使、隋滅亡後は遣唐使によって継続的に中国伝統医学の輸入が行われました。753年には有名な鑑真和尚が仏教の教えとともに朝鮮人参、桂皮、甘草、大黄などの生薬を日本に持ち込み、それらは正倉院に保管されました。生薬の一部は1000年以上の時を経て、なんと現在で薬効成分が失われていないそうです。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学の歴史 (2)
日本における漢方の歴史、その前編は中国からの輸入の歴史でした。後編は輸入されてきた中国伝統医学を日本人に合う形に変えていった時代から今日に至ります。前編で述べたようにまず中国伝統医学は朝鮮半島から日本へ流入が始まり、その後は飛鳥時代、奈良時代、そして平安時代前期まで遣隋使や遣唐使といった交易の中で継続的に伝来してきました。
時はさらに進み室町時代の1400年代になると中国(明)との交易が活発になります。この時期は東シナ海で海賊行為を行っていた倭寇と正規の貿易団を区別するため勘合貿易が行われていた頃です。
戦国時代の幕が上がった1500年頃、明から帰ってきた留学者たちによって金元時代のさまざまな治療理論が日本に伝わってきました。この金元時代流の医学は田代三喜(たしろさんき)やその弟子である曲直瀬道三(まなせどうざん)らによって発展し、繁栄します。
その一方で江戸時代、1600年代頃になると複雑化する中国伝統医学の理論に対して疑問が提起され始めました。それまで輸入され続けてきた理論重視の医学から実践重視へと大きく潮流が変わってきたのがこの時代です。
理論重視から実践的な治療への原点回帰を目指した勢力は自分たちを古方派(こほうは)と呼びました。これは同勢力が中国において紀元後200年頃、中国において漢時代の後期に当たりに書かれた傷寒論や金匱要略を治療の中心に据えたからです。
吉益東洞(よしますとうどう)ら古方派は傷寒論や金匱要略を大切にしつつ、より日本人に合う独自の治療法を模索します。中国では重視されなかった腹部の状態から合う薬を考える腹証の発展はその代表格です。この背景には鎖国によって中国から医学に関する情報が入りにくくなっていたことも影響しているでしょう。
その後、江戸時代中期になると古方派、陰陽五行論など金元時代の医学を基礎とする理論重視の後世方派(ごせいほうは)または後世派、良いものは幅広く取り込もうとした折衷派(せっちゅうは)などが立ち並びます。そしていよいよ鎖国の時代から開国の時代になると、日本にもオランダを中心に西洋医学が輸入されてきます。
明治時代になると中国伝統医学を基礎にする医学派は自らの医学を「漢方」と名乗ります。つまり今日まで続く「漢方」という言葉の歴史は意外にも浅く、この時代に急拡大してきた西洋医学であるオランダ医学などと自らを差別化するために生まれたという経緯があります。
文明開化の明治時代から大正時代にかけて漢方は西洋医学(主にドイツ医学)の勢いに押されがちになります。今日まで至る「医学といえば西洋医学」という潮流が決定的になった時代といえるでしょう。漢方の治療家たちが日本政府へ漢方医学の重要性を訴えるも勃発した日清戦争や日露戦争などの影響を受けて、その存在が顧みられる機会は失われてしまいます。
昭和に入ると細々と生きながらえていた漢方医学の効果が徐々に見直されてゆきます。くわえて戦後には服用や保管が容易なエキス製剤も開発され、漢方薬の幅広い普及に貢献しました。そして平成以降は西洋医学とは異なる治療の選択肢として漢方は再評価され(くわしくはこちら)、今も連綿と受け継がれているのです。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学を築いた先人たち (1)
前ページでは漢方医学の歴史を前編と後編に分けて解説いたしました。ここからは既出の歴史を踏まえて、今日の漢方医学を築いた先人たちにスポットを当ててゆきます。一部には伝説上の人物も含まれていますが、学術的に重要と考えて収載しました。
黄帝(こうてい)
黄帝は古代中国における伝説上の人物です。伝説では黄帝は生まれてすぐに言葉を話し、聡明でありながら精悍であったとされています。有力者同士が戦争を繰り広げる中、それを仲裁して平和な時代を築いたといわれています。まさに古代中国版「スーパーマン」というところです。
その黄帝が著したとされるのが黄帝内経(こうていだいけい)であり、中国最古の医学書です。しかしながら、実際に黄帝が書いたものではなく(皇帝自身が伝説上の人物なので当たり前ですが…)、複数の人物と長い時間をかけて書き綴られたという説が有力です。黄帝内経は紀元前200年頃の前漢の時代に成立したとされています。
そのような黄帝内経ですが、内容は黄帝が医学のエキスパートである岐伯(きはく)に質問をし、その答えをまとめるQ&A形式で構成されています。具体的には陰陽論や五行論といった古代中国の世界観、そしてそれに基づいた人体における気(き)・血(けつ)・津液(しんえき)と五臓六腑(ごぞうろっぷ)の働きなどが紹介されています。
他にも季節ごとの養生法、症状と病邪の関係、鍼灸を中心とした治療法などが載っています。その一方で生薬(漢方薬)を用いた治療法の記述は意外にも少ないものでした。
神農(しんのう)
神農もまた黄帝と同じように伝説上の人物であり、古代中国における農耕と薬の祖とされています。神農は人々に農具の作り方や田畑の耕し方を伝えたことから「神農」と崇められました。くわえて神農はありとあらゆる草根木皮を食し、それらが薬となることを示しました。
その経験から生まれたのが神農本草経(しんのうほんぞうきょう)であり、中国最古の本草書(個々の生薬の効果を記録した書)といわれています。実際に神農本草経が生まれた時代には諸説がありますが後漢の時代(紀元後200年頃)とされています。著者に関しても詳しく明らかになっていません。
この神農本草経には365種類の薬が収載されており、内訳は植物由来のものが252種、動物由来のものが67種、そして鉱物由来のものが46種となっています。さらにこれらを上薬・中薬・下薬に分類されています。
上薬は普段から服用していると健康増進効果があり無毒とされています。中薬は有毒なものもあるので養生や治療に用いるものです。そして下薬は基本的に有毒なものであり、慎重に治療にのみ用います。
神農本草経における上記の分類法は既にこの時代から治療よりもその予防や養生を非常に重視していたことを示しています。1800年以上前からこのように考えていたという事実はまさに驚くべきことです。
張仲景(ちょうちゅうけい)
張仲景(生年不明~219)は中国の長沙を治めていた人物です。この張仲景が著したとされるのが漢方医学において最も重要とされている文献、傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)です。成立は紀元後200年頃、後漢の時代であり神農本草経とほぼ同時代に生まれたとされています。
張仲景は自分の一族の多くを流行性の病である傷寒によって失ったことをきっかけに傷寒雑病論を作り上げました。しかし、実際には複数の人物による共著という説が有力です。傷寒雑病論は後に感染症治療を中心に扱う部分が傷寒論(しょうかんろん)、慢性病を扱う部分が金匱要略(きんきようりゃく)とそれぞれ独立した文献として分かれてゆきました。
これら傷寒論と金匱要略には本格的な漢方薬を用いた治療が登場しています。現代の日本でも用いられている葛根湯、当帰芍薬散、八味地黄丸などの超有名漢方薬も傷寒論や金匱要略に収載されています。今日、頻用されている漢方薬の多くが両書に載っていることからもその重要性がわかります。
日本の江戸時代においては過度に複雑化していた治療理論を極力排除し、古来のよりシンプルな治療を行うべきという運動が盛んになりました。そういったイデオロギーをもった治療家たちが治療方針の軸としたのが傷寒論や金匱要略でした。この潮流は今日における漢方治療にも影響を及ぼしています。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学を築いた先人たち (2)
日本に中国伝統医学が導入され始めたのは紀元後400年頃の大和時代、朝鮮半島を経由して始まったとされています。その後は遣隋使や遣唐使に代表される中国との直接的な交易も介して知識の輸入が行われました。時代は進み室町時代になると模倣一辺倒に近かった日本の医学にも変化が訪れます。
田代三喜(たしろさんき)
日本に初めて中国伝統医学が上陸してから1000年以上の時を経た16世紀、室町時代の医師である田代三喜(1465~没年不明)は中国(当時は明)に約10年、留学しました。田代三喜は明で金元時代に発展した李朱医学を学び、その知識を日本に導入した人物として有名です。「李朱医学」とは李東垣(りとうえん)と朱丹渓(しゅたんけい)が提唱した医学を指します。
金元時代の医学は陰陽論、五行論、六気といった理論を臨床レベルに導入したという点で革命的なものでした。今風に表現すれば医学界のイノベーションが金元の時代に起こったということです。
田代三喜が日本に広めた李朱医学はその後の日本における漢方医学の礎となりました。この金元時代の医学は傷寒論や金匱要略の時代よりも経時的に「後」の流れなので、後世方(ごせいほう)と呼ばれます。したがって、田代三喜は後世方派の元祖といえる存在です。
李東垣(りとうえん)
李東垣(1180~1251)は金元時代を代表する医師です。元の名は李杲(りこう)であり、晩年に李東垣と号しました。李東垣は人々が病気になる原因は脾胃(消化器系)が弱まったためと考え、それを治すことを治療の核としました。簡単に表現すれば李東垣の治療方針は胃腸を元気にして病気を治したり、病気にならない身体づくりを行うことといえます。
この李東垣の考えを支持する一派は温補派や補土派と呼ばれました。なぜ「土」なのかというと、五行論における脾(ひ)は土のグループに属すると考えられているからです。
李東垣の代表的な著書に脾胃論(ひいろん)や内外傷弁惑論(ないがいしょうべんわくろん)が挙げられます。前者には今日の日本でも頻繁に用いられている半夏白朮天麻湯、後者には補中益気湯が収載されています。
朱丹渓(しゅたんけい)
朱丹渓(1281~1358)もまた金元時代をリードした医師の一人です。本名は朱震亨(しゅしんこう)でしたが、今日の浙江省の「丹渓」という場所で暮らしていたので「朱丹渓」と呼ばれるようになりました。
朱丹渓の治療方針は不足している陰を補うことで、相対的に亢進している陽を鎮めることにありました。よりシンプルに述べれば朱丹渓の治療は陰陽の崩れたバランスを回復する滋陰降火を基調としたものでした。この為、朱丹渓の治療方針を支持するグループは養陰派や滋陰派と呼ばれました。
曲直瀬道三(まなせどうざん)
曲直瀬道三(1507~1594)は日本に金元時代の医学、主に李朱医学を伝えた田代三喜の弟子にあたります。したがって、曲直瀬道三は田代三喜と並ぶ後世方派の代表的人物といえます。
曲直瀬道三は田代三喜の教えをもとに李朱医学を継承しました。その一方であまりに複雑な理論をシンプルに解釈して日本の風土に合う形に発展させました。医師としての実力も高く、時の権力者である毛利元就、織田信長、豊臣秀吉も曲直瀬道三を重用したといわれています。
くわえて曲直瀬道三の業績はその医学を教える学校である啓廸院(けいてきいん)を設立したことです。啓廸院の卒業生たちはその後も後世方派として活躍してゆきます。曲直瀬道三の著書である啓迪集も実用性の高い医学書として高い評価を得ています。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学を築いた先人たち (3)
室町時代以降、日本の医学は金元医学の影響を大きく受けながら発展しました。この金元医学を治療の中心に据える後世方派が隆盛を極めた時代でもあります。その一方で江戸時代中期になると後世方派の理論を重視する流れに疑問も提起され始めました。さらに江戸時代の後期、鎖国の時代から開国を経て医学の世界にも未曾有の変化が訪れます。
吉益東洞(よしますとうどう)
いつの時代もある一方向にベクトルが偏ると、それを軌道修正しようとする動きが働きます。まさにそれが起こったのが江戸時代中期、理論に拘泥する医学よりも実践的な治療を重視するべきという運動が巻き起こります。
その運動の中心にいた医師の名古屋玄医(なごやげんい)は治療方針を後漢時代に張仲景が著した傷寒論と金匱要略に求めます。傷寒論などへの回帰に賛同した治療家集団は自分達を古方派と称し、金元医学を基調とする者たちを後世方派として差別化を図ります。
この古方派の中でも異質な存在感を放つのが吉益東洞(1702~1773)です。吉益東洞はすべての病気は体内に潜む毒が起こしており、その毒の位置によって病態が異なるという「万病一毒説」を提唱しました。
治療にはこの毒を排除するべく薬効の強い生薬を多く用いたといわれています。まさに「毒をもって毒を制す」という治療法です。もともと吉益東洞は医師を志す前は武道で身を立てようと考えていました。このような背景は非常に攻撃的で、金元医学とは相反する吉益東洞流の治療スタイルの源泉なのかもしれません。
くわえて吉益東洞は後世方派の唱える陰陽五行論などの諸理論を完全に否定する一方、腹診を治療の核とするなど独自色を発揮します。さらにシンプルに患者に現れている症状からどのような処方が合うのかをまとめた類聚方(るいじゅほう)や、生薬個々の働きを論じた薬徴(やくちょう)は高い評価を得ました。
吉益東洞の思想や治療法はあまりにラジカルな面もありますが、以後の日本における漢方医学の方向性を決定付けるほどの実用的魅力を含んだものでもありました。
山脇東洋(やまわきとうよう)
山脇東洋(1705~1762)は上記で挙げた吉益東洞とほぼ同じ時代を生きた古方派の医師です。もともと古方派は後世方派と比較して革新的な気風があり、山脇東洋もまたその例外ではありません。
山脇東洋は1754年、京都において日本初となる人体解剖を行い、その成果を蔵志(ぞうし)にまとめて刊行しました。 この歴史的事実は非常に有名ですが、山脇東洋は傷寒論などの古文献の研究や翻訳でも実績を残しています。
吉益南涯(よしますなんがい)
吉益南涯(1750~1813)はその名が示す通り、吉益東洞の長男にあたります。父の吉益東洞を含め古方派は病気には何か病的な存在が関与していると考えていました。
一方の吉益南涯は毒の存在を認めつつ、毒の影響で身体内の気・血・水のバランスに異常が発生した結果として病気となると唱えたのです。 この考え方は今日の日本に広まっている気血水論の礎になっています。
花岡青洲(はなおかせいしゅう)
花岡青洲(1760~1835)は吉益南涯に師事して漢方医学を学ぶ傍ら、当時最先端のオランダ医学(蘭学)も習得していました。つまり、花岡青洲は漢蘭折衷派のトップランナーといえます。
花岡青洲の生きた江戸時代後期は後世方派の理論と古方派の実用性を融合させる運動が盛んになっていました。このような時代的背景が漢方と蘭学という異なる医学をまたがって学ぶ土壌を生んでいたのかもしれません。
花岡青洲は1804年に世界で初めて全身麻酔薬を施し外科手術(乳がんの摘出手術)を行ったことで有名です。この時に用いられた全身麻酔薬は蔓陀羅花を中心に構成された通仙散(別名:麻沸散)というものであり、完成に約20年を費やしたといわれています。この通仙散開発のエピソードは小説「花岡青洲の妻(著者:有吉佐和子)」の題材にもなりました。
外科手術に関しては上記の乳がん摘出以外にも尿路結石の摘出や関節障害の治療もおこなわれました。くわえて花岡青洲は通仙散の他にも十味敗毒湯、紫雲膏、中黄膏といった今日でも用いられている漢方処方を生み出しています。
浅田宗伯(あさだそうはく)
浅田宗伯(1815~1894)は幕末から明治初期に活躍した折衷派の医師であり、江戸時代最後の漢方医学界の大家と呼ばれます。その腕は確かなものであり、徳川第14代将軍の家茂や後の大正天皇である明宮嘉仁の治療にもあたりました。時にはフランス公使の重い腰痛の治療を成功させてナポレオン三世から感謝の品が送られました。今日でも有名な浅田飴のもととなる処方を考案したのも浅田宗伯といわれています。
幅広い活躍から「江戸時代最後の漢方医学界の大家」と称賛されましたが、換言すれば浅田宗伯以降、漢方界を代表する医師はなかなか生まれなかったことを示しています。これは明治維新後、日本は近代化の一環としてドイツ医学を中心とした西洋医学を国定医学に採用したことが最大の理由です。浅田宗伯は人脈を生かしてこの決定を覆そうと奔走しますがその願いは叶いませんでした。
しかし、浅田宗伯が弟子たちの教材として普段から用いていた漢方処方とその効能を記した勿誤薬室方函口訣(ふつごやくしつほうかんくけつ)の評価は極めて高いものです。折衷派の浅田宗伯らしく勿誤薬室方函口訣には傷寒論や金匱要略以外の文献からも幅広く優れた処方が網羅されています。そして同書に収載されている漢方処方の多くは今日でも頻繁に用いられており、現在の漢方医学を支えています。
森道伯(もりどうはく)
森道伯(1867~1931)は明治時代から昭和初期にかけて独自の漢方医学体系である一貫堂医学(いっかんどういがく)を創始した治療家です。この「一貫堂」という名称はただ一人になっても漢方医学再興の道を貫くという意味が込められています。
森道伯の提唱した一貫堂医学においては個々人の体質を解毒証体質・臓毒証体質・瘀血証体質という三大証に分け、それらに対応する処方を多用しました。具体的には解毒証体質には柴胡清肝湯、荊芥連翹湯、竜胆瀉肝湯、臓毒証体質には防風通聖散、そして瘀血証体質には通導散が盛んに用いられました。
今日的な表現をすれば解毒証体質はアレルギー体質、臓毒証体質はメタボリックシンドローム体質、瘀血証体質は血行不良で顏色が赤黒く生理不順や生理痛に悩む女性に多い体質です。これらの体質は固定的なものではなく、例えばひとりの人間が「解毒証体質と臓毒証体質の傾向を半々でもっている」と捉える場合もあり、各処方を調節したものが実際には使用されていました。
これらの病気や症状は現代においても大きな健康問題であり、一貫堂医学に基づいた治療を行っている信奉者は根強くいます。森道伯が「一貫堂」の名前に込めた意味とともにその医学は今も生き続けています。
和田啓十郎(わだけいじゅうろう)
和田啓十郎(1872~1916)は明治時代から大正時代にかけて活躍した漢方医です。和田啓十郎は幼少の頃、姉の病気が漢方薬によって回復する姿を目の当たりにして漢方の道を志しました。その後の日本は近代化が急速に進み、日清戦争にも勝利した結果、社会全体の西洋化の流れはもはや止めることのできないものになっていました。
漢方医学もこの潮流に押し流され、風前の灯ともいえる状態に追い込まれます。そんな中、和田啓十郎が1910年(明治43年)に著した医界之鉄椎(いかいのてっつい)は瀕死状態の漢方医学の重要性を社会に訴えました。同書は大きな反響を呼び、それまで細々と生きながらえてきた漢方医学復興の橋頭堡となります。
湯本求真(ゆもときゅうしん)
湯本求真(1876~1941)もまた前出の和田啓十郎と同じ時代を生きた漢方医です。湯本求真は和田啓十郎が著した医界之鉄椎を読み漢方の道を志しました。1927年(昭和2年)に刊行した皇漢医学(こうかんいがく)は日本のみならず中国でも高い評価を得ました。
湯本求真は実際の治療においては傷寒論・金匱要略に収載されている処方を多く用いたといわれています。これはやや憶測も入りますが湯本求真の漢方の師は尾台榕堂(おだいようどう)といわれ、同氏の師を遡ると古方の大家、吉益東洞に行き着くからかもしれません。
湯本求真のもとには多くの弟子が集まり、下記の大塚敬節のように漢方医学の復興運動を展開しました。西洋医学の大波によって漢方医学が押し流されてしまった時代の中で、湯本求真のまいた種は次世代で結実してゆきます。
大塚敬節(おおつかけいせつ 又は よしのり)
大塚敬節(1900~1980)は昭和の時代を代表する漢方医です。無論、昭和の時代の医学部教育は西洋医学を基盤にしたものでした。大学を卒業して医師になった大塚敬節は漢方医学に興味を持ち、上京して湯本求真に師事しました。そこで主に古方派として漢方を学び傷寒論と金匱要略の研究を続けました。独立後は東京で修琴堂大塚医院を開設して治療を行いつつ、精力的に漢方医学復興運動にも注力しました。
この運動は実を結び、浅田宗伯の時代以降、長く低迷していた漢方は途絶えることなく再評価され今日も生き続けています。1950年代後半には漢方薬の有効成分を抽出して得られるエキス製剤が発明され、その服用や管理のしやすさから漢方薬普及の大きな後押しにもなりました。
やや余談になりますが大塚敬節は50代の前半、高血圧症による眼底出血や頭痛に苦しんでいました。いくつかの処方を試すもうまくゆかず、とうとう自身の創作した処方によって失明を免れたと語っています。この処方は四物湯(地黄、芍薬、当帰、川芎)に釣藤鈎、黄耆、黄柏を加えたもので、後に七物降下湯(しちもつこうかとう)と命名されました。
この七物降下湯は今日の医療現場でも用いられており、エキス製剤としても製造されています。したがって、七物降下湯は生まれてまだ半世紀少々しか経っていない「日本において最も若い漢方薬」といえます。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学を伝えてきた文献 (1)
漢方医学を築いた先人たちはその知識を多くの文献として残しました。今日の漢方医学があるのは無数の先人たちが残してくれた知識の結晶でもあります。まずこのページでは中国伝統医学において最も重要といわれる黄帝内経・神農本草経・傷寒雑病論(傷寒論と金匱要略)について概説いたします。これらは 漢方医学の歴史や 漢方医学を築いた先人たちでも登場しますので、ぜひ照らし合わせながらご覧ください。
黄帝内経(こうていだいけい)
黄帝内経は紀元前200年頃の前漢の時代に成立したとされる中国最古の医学書であり、素問(そもん)と霊枢(れいすう)の二部から構成されています。残念ながらオリジナルは現存していません。
その一方で独自の注釈などを加えた写本は数多く残されています。代表的なものに黄帝内経太素(こうていだいけいたいそ)があり、遣唐使を通じて日本に輸入され国宝として現存しています。
黄帝内経の著者はタイトルにもある黄帝ではなく、前漢時代よりも約500年前の春秋時代頃(日本は縄文時代)から複数の人間の手によって時間をかけて編纂されたとされています。したがって、明確な著者は不明です。
もしかすると著者たちは伝説上の人物であり、超人的な能力を持った偉大な帝王である黄帝の名を冠して文献の権威を高めようとしたのかもしれません。実際にその価値は極めて高く、後述する神農本草経、傷寒雑病論(傷寒論と金匱要略)と並んで黄帝内経は中国伝統医学史においてその基礎理論を示した最も重要な文献といわれています。
この黄帝内経の内容としては陰陽五行論を背景とした宇宙・自然・人間の密接な関連、五臓六腑の役割、経絡の説明と鍼灸を用いた治療法、病気の種類、一年を通じて病気にならないための養生法などが細かく分かれて収載されています。現代的な表現をすれば古代中国における生理学、病理学、衛生学、そして鍼灸を中心とした診断学と治療学の論文集といった体裁です。
黄帝内経は上記の通り鍼灸を用いた治療に多くのページを割いており、生薬を用いた治療法は約10種類程度しか載っていません。くわえて傷寒論に収載されている葛根湯のように現代においてもエキス製剤化されているような「現役」の処方はありません。
神農本草経(しんのうほんぞうきょう)
神農本草経は紀元後200年頃の後漢の時代に成立したとされる中国最古の本草学書です。諸説はありますが下記の傷寒雑病論(傷寒論と金匱要略)とほぼ同時代に生まれたと推測されています。
神農本草経の著者は神農ということになっていますが、神農自体が伝説上の人物なので明確には明らかにはなっていません。おそらく長い年月と複数の人間の経験(人体実験)を土台にして上げられたと考えられます。
神農本草経のタイトルにもある「本草」とは生薬として用いられる植物・動物・鉱物の総称であり、本草学は生薬単体の名称や形態を整理し、薬効や用法などを研究する学問です。神農本草経を含めて本草学書はそれらの情報をまとめた「生薬辞典」のようなものです。
神農本草経のオリジナルは失われており、その姿は注釈などを加えた写本から推測されています。有名な写本に陶弘景(とうこうけい)が紀元後500年頃に製作した神農本草経集注(しんのうほんぞうきょうしっちゅう)や神農本草経集(しんのうほんぞうきょうしゅう)があります。
神農本草経には植物薬252種、動物薬67種、鉱物薬46種の合計365種が収載されており、それらは上薬・中薬・上薬に分類されています。内訳は上薬120種、中薬120種、下薬125種に分けられ、効能や使用法が書かれています。
上薬には長期的に服用しても害はなく、健康を維持して寿命を延ばすような生薬が含まれます。中薬は毒にもなりえるので養生や治療に慎重に用いる生薬になります。そして下薬は基本的に有毒な生薬なので治療にのみ用いて長く服用してはいけません。代表的な例として人参や地黄は上薬、当帰や芍薬は中薬、そして大黄や附子は下薬に分けられています。
上薬・中薬・上薬という分類を見ると太古の時代から治療よりも養生、つまり病気になる前にそれを防ぐことを重要視していたことが神農本草経から読み取れます。さらに上薬には上記の人参や地黄にくわえて山薬(ヤマイモ)や大棗(ナツメ)など食品として今日でも用いられているものも多く、医食同源の思想も描かれています。
他にも神農本草経には複数の生薬を組み合わせることでその作用を増幅させたり、毒性を弱めたりすることが示されています。この考え方は後に生まれる漢方薬の基礎的知識となっています。
傷寒論(しょうかんろん)
傷寒論はもともと傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)という文献の急性感染症治療を取り扱った部分が分離独立して生まれました。もう片方は金匱要略(きんきようりゃく)という急性感染症以外の病気に対応するための文献となりました。
傷寒論(傷寒雑病論)は紀元後200頃の後漢の時代に成立したとされています。傷寒論における「傷寒」とは急性のやや重い感染症のことであり、インフルエンザや腸チフスなどを指しているといわれています。
著者は中国の長沙という地域を治めていた張仲景(ちょうちゅうけい)という人物とされています。しかし、実際には複数の人物の手によって編纂されたという説が濃厚です。
残念ながら傷寒論のオリジナルは完成後まもなく失われてしまい、晋の時代に高い完成度で再編纂されたといわれていますがこれも程なくして消失。オリジナルを知る手がかりとしては宋の時代に復刻出版された宋板(宋版)傷寒論や大塚敬節が発見した康平傷寒論などが有力とされています。その一方で真偽の議論は依然として続いています。
傷寒論は黄帝内経、金匱要略、神農本草経とともに中国伝統医学史において最も重要な文献といわれています。この「重要性」は考古学的なものに限定されず、実用性の面でも今日において力を発揮します。江戸時代に勃興した日本の古方派は特に傷寒論を重視しました。
「感染症対策マニュアル」ともいえる傷寒論の特徴は患者の病態を六つに分けて、各ステージにおける治療法を網羅している点です。これらのステージは六病位や三陰三陽病と呼ばれ、太陽病・陽明病・少陽病・少陰病・太陰病・厥陰病から構成されています。基本的に病邪(今風に表現すればウイルスや病原菌です)は身体の表面から侵入してゆき、徐々に身体内部を犯してゆくと傷寒論では述べられています。
したがって、治療者は患者の症状から患者はどの病位にあるのかを判断し、そこから適した漢方薬を導き出すことが治療のプロセスとなります。この診断から治療までの一連の流れを六経弁証(ろっけいべんしょう)と呼びます。
例えば傷寒論による太陽病の定義は「太陽の病と為すは脈浮、頭項強痛して悪寒す」とされます。これは「脈をとると体表の近くにその流れを感じ、頭やうなじにこわばりがあり、寒気を感じる」状態です。
さらに読み進めると「太陽病、項背強ばること几几、汗なく悪風するは、葛根湯之を主(つかさど)る。」とあります。これは「後頭部から肩甲骨の辺りがこわばって、汗はあまり出ず、風に当たると寒気を感じるようだったら葛根湯を服用すれば治る」という意味です。わかりやすく葛根湯で治る病態が書かれています。
傷寒論を読んでいる「医者が誤って……」という文にしばしば遭遇します。この文句の後には「その際は○○しなさい」という文が続きます。これは文字通り、六経弁証が間違っていた際の対処方法ということになります。このような記述があることからも傷寒論の完成度の高さや今日でも評価を受け続ける実用性の高さが感じ取れます。
傷寒論を出典として現在も頻用される漢方薬としては茵蔯蒿湯、黄連湯、葛根黄連黄芩湯、葛根湯、甘草瀉心湯、桔梗湯、桂枝加葛根湯、桂枝加桂湯、桂枝加厚朴杏仁湯、桂枝加芍薬湯、桂枝加芍薬大黄湯、桂枝湯、桂枝人参湯、桂麻各半湯、呉茱萸湯、五苓散、柴胡加竜骨牡蛎湯、柴胡桂枝乾姜湯、柴胡桂枝湯、四逆散、梔子柏皮湯、炙甘草湯、芍薬甘草湯、芍薬甘草附子湯、小陥胸湯、生姜瀉心湯、小建中湯、小柴胡湯、小承気湯、小青竜湯、真武湯、大柴胡湯、大承気湯、調胃承気湯、猪苓湯、桃核承気湯、当帰四逆加呉茱萸生姜湯、人参湯、半夏瀉心湯、白虎加人参湯、麻黄湯、麻黄附子細辛湯、麻杏甘石湯、麻子仁丸、苓桂甘棗湯、苓桂朮甘湯などが有名です。なお一部は下記の金匱要略と重複しており、名称は現在において一般的に用いられている形で表記しています。
金匱要略(きんきようりゃく)
上記の傷寒論の項目でも述べた通り、金匱要略は傷寒雑病論という文献の雑病、つまりは急性の感染症以外の慢性病を取り扱った部分が分離独立して生まれました。金匱要略(傷寒雑病論)は紀元後200頃の後漢の時代に成立したとされています。
著者は傷寒論と同様に張仲景とされていますが、やはり複数の人物の手によって編纂されたものと考えられています。残念ながら金匱要略もまたオリジナルは失われています。宋の時代(紀元後1000年頃)に偶然発見された断片的な写本を再編集したものが今日まで伝わっています。
金匱要略の特徴は幅広い慢性病を取り扱っており、「婦人妊娠病」のように大まかな疾患のカテゴリーが示されている点です。現代風に収載されている疾患のカテゴリーを表現すれば循環器系疾患・呼吸器系疾患・消化器系疾患・泌尿器系疾患・皮膚科系疾患・産婦人科系疾患・精神科系疾患などを網羅しています。
より細かく見てゆくと慢性疲労や不眠症のような今日でも大きな問題になっている病気から、落馬した際のケアや首つりをした者への応急手当などややエキセントリックで驚いてしまうような項目もあります。くわえて食べ物を選ぶ際の注意や食べ合わせなど、オリジナルの金匱要略に記載が本当に合ったのか疑問視される項目も見受けられます。
現代の日本において金匱要略にも載っているような慢性病は依然として大きな社会的問題です。そのような背景もあり、金匱要略に収載されている漢方薬は今日の医療現場において「エース級」として活躍する「現役選手」が極めて多いです。簡単に比較はできませんが、その活躍の幅は傷寒論収載処方を凌ぐほどです。
ほんの一例として貧血やむくみを改善する当帰芍薬散、つらい生理痛や子宮筋腫にも有効な桂枝茯苓丸、不正出血や痔の出血などに用いられる芎帰膠艾湯、動悸や不安感を除く桂枝加竜骨牡蛎湯、加齢による腰痛や頻尿を癒す八味地黄丸、乾燥した咳を鎮める麦門冬湯、下半身を中心とした冷えを緩和する苓姜朮甘湯などは今でも不可欠な漢方薬が金匱要略にはいくつも収載されています。
上記に加えて金匱要略を出典として現在も頻用される漢方薬としては茵陳蒿湯、茵陳五苓散、温経湯、越婢加朮湯、黄耆桂枝五物湯、黄耆建中湯、葛根湯、甘草瀉心湯、桔梗湯、桂枝加黄耆湯、桂枝加桂湯、桂芍知母湯、桂枝湯、呉茱萸湯、五苓散、柴胡桂枝湯、酸棗仁湯、三物黄芩湯、炙甘草湯、小建中湯、小柴胡湯、小承気湯、小青竜湯、小青龍湯加石膏、小半夏加茯苓湯、沢瀉湯、大黄甘草湯、大黄牡丹皮湯、大建中湯、大柴胡湯、大承気湯、猪苓湯、人参湯、排膿散、排膿湯、半夏厚朴湯、半夏瀉心湯、白虎加人参湯、茯苓飲、防已黄耆湯、麻杏薏甘湯、麻子仁丸、苓甘姜味辛夏仁湯、苓桂甘棗湯、苓桂朮甘湯などが有名です。なお一部は傷寒論と重複しており、名称は現在において一般的に用いられている形で表記しています。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
漢方医学を伝えてきた文献 (2)
このページでは黄帝内経、神農本草経、そして傷寒雑病論(傷寒論・金匱要略)の書かれた時代以降、後漢時代以降の代表的な文献のごく一部を紹介いたします。基本的には古い文献の順になっていますので、ページの下に行くにつれて現代に近付いてゆきます。なお、文献名の前に※が付いているものは日本生まれの文献になります。
下記は諸説ある中で大まかな中国の歴史(時代の区切り)と、その時代の代表的な文献になります。読み進める上で参考にしてください。
秦時代(紀元前221~紀元前207)
前漢時代(紀元前207~紀元前8)………黄帝内経
新時代(紀元前 8~紀元後 25)
後漢時代(25~220)………神農本草経、傷寒雑病論(傷寒論・金匱要略)
三国時代(220~265)
晋時代(265~420)
南北朝時代(420~589)………小品方
隋時代(589~618)………諸病源候論
唐時代(618~907)………備急千金要方、千金翼方、外台秘要、※大同類聚方
五代十国時代(907~960)
宋時代(960~1279)………※医心方、太平恵民和剤局方、小児薬証直訣
宋の時代に含まれるように金朝(1115~1234)
元時代(1270頃~1368)………内外傷弁惑論、脾胃論
明時代(1368~1644)………本草綱目、万病回春
清時代(1644~1912)………※勿誤薬室方函、※勿誤薬室方函口訣
中華民国(1912~)と中華人民共和国(1949~)が併存………※漢方診療医典
小品方(しょうひんほう)
小品方は陳延之(ちんえんし)によって南北朝の時代にあたる450~470年頃に書かれた医学書です。小品方は後の唐の時代において国定の医学教科書に採用されており、当時では傷寒論と比肩する文献とされていました。
この頃、すでに日本には遣隋使や遣唐使を通じて中国大陸から多くの医学書が伝わっていました。小品方もまた導入され、今日でも日本においてその一部は現存しています。701年に日本において施行された大宝律令でも小品方は神農本草経集注や素問と並び国定教科書の指定を受けました。したがって、小品方は日中共通の公的な医学テキストの先駆けといえます。
諸病源候論(しょびょうげんこうろん)
諸病源候論は巣元方(そうげんほう)が隋の時代にあたる610年に完成させた病理学書です。当時の隋の皇帝、煬帝の命令で作成されたといわれています。主に病気の名前、症状、そして原因を記載したもので、内科系疾患から外傷まで幅広く紹介されています。その一方で傷寒論や金匱要略とは異なり具体的な治療法には触れられていません。
諸病源候論は上記の通り治療法は記載されていませんが、その病気の分類方法は後に生まれる文献にも影響を及ぼしました。下記に登場する王燾が著した外台秘要なども同書の病気分類をベースに処方が紹介されています。
備急千金要方(びきゅうせんきんようほう)
備急千金要方は孫思邈(そんしばく)によって唐の時代にあたる650年頃に作成されました。しばしば略して千金要方とも呼ばれます。備急千金要方はそれまで存在した多くの処方集(漢方薬のリスト)から、有用で緊急時に活用できる処方をまとめた医学書です。
備急千金要方は身体の弱い女性や子供の病気に比重が置かれているという特徴があります。幅広い疾患についての薬物治療法の他に備急千金要方には食事の注意、呼吸法、鍼灸治療法なども記載されています。備急千金要方が完成した後、傷寒論の記述を反映させて同書を補完した千金翼方(せんきんよくほう)も作成されました。
孫思邈は非常に有能な治療家でしたが名誉欲は薄く、当時の皇帝たちの招きをことごとく断り隠居。身近な人々の治療を熱心に行っていました。自身も幼少は病気を患い、家族に迷惑をかけたといわれており、そのような背景が備急千金要方や千金翼方に繋がっているのかもしれません。孫思邈はその仁徳の高さから今日の中国において最も人気がある医師の一人であり「薬王」の名で尊敬されています。
今日でも用いられる温胆湯、当帰湯(同名処方があるのでしばしば千金当帰湯)、堅中湯、補肺湯は備急千金要方に収載されています。
外台秘要(げだいひよう)
外台秘要は王燾(おうとう)が唐の時代にあたる752年頃に完成させたとされる医学書です。王燾はもともと病弱であり、母親もまた病気がちであったことが医学に目覚めるきっかけであったとされています。
王燾は医事を司る公職に就いていたので国立図書館に通いつめ、膨大な数の医学書を引用して外台秘要を作り上げました。外台秘要の特徴としてそこに収載した処方の引用元が細かく記述されている点が挙げられます。これにより外台秘要が登場する以前の文献の姿をより知ることが可能となり、医史学的価値も高い医学書といわれています。
外台秘要に収載されている処方のうち延年半夏湯、神秘湯、独活葛根湯などは今日の日本においても用いられています。
大同類聚方(だいどうるいじゅほう)
大同類聚方は日本において平安時代の初期にあたる808年に作成された日本独自の医学をまとめた文献です。桓武天皇の命令により出雲広貞(いずものひろさだ)、安倍真直(あべのまなお)らが編纂した日本初の医学書といわれています。
この大同類聚方が作成された経緯は大陸から遣唐使などを通じて「輸入」されてくる中国伝統医学に圧倒され、日本古来の医学が滅んでしまうことを防ぐためとされています。遣唐使自体は838年を最後に中止されましたが、すでに主要な文献は日本に導入されていたと考えられています。大同類聚方はそのような時代背景が生み出した医学書です。
その一方で大同類聚方は現存しておらず、謎の多い文献でもあります。その内容自体も純粋に日本独自のものだったのか疑問も提起されています。
医心方(いしんほう)
医心方は丹波康頼(たんばやすより)によって平安時代の中期にあたる984年に作成された現存する日本最古の医学書です。大同類聚方は連綿と受け継がれてきた日本独自の医学が記録されているのに対し、医心方には隋や唐から導入された文献が多く引用されています。
医心方は完成後に宮廷へ献上され厳重に管理されました。そのために実態が広く一般にも明らかになったのは江戸時代後期とされています。すでに中国でも失われてしまった重要な文献が医心方には引用されているため、歴史的価値もまた非常に高い医学書といえます。
その価値の高さを受けて医心方は完成から1000年後の1984年、国宝に指定され今も東京国立博物館に収蔵されています。 こちらの東京国立博物館のホームページ からその一部を目にすることができます。内容としては陰陽五行論といった理論の多くが省略され、実用性を重視した体裁となっています。
やや余談になりますが、著者の丹波康頼の子孫たちはその後も代々、宮廷に仕える医師となりました。その子孫には現在の東京薬科大学の前身である東京薬学専門学校初代校長の丹波敬三や俳優であり著名な心霊研究家(?)の故・丹波哲郎が含まれます。
太平恵民和剤局方(たいへいけいみんわざいきょくほう)
太平恵民和剤局方は陳師文(ちんしぶん)らを中心に宋の時代にあたる1110年頃に編纂された医学書です。後に最低でも4回の改訂を経てその内容も充実してゆきました。しばしば略して和剤局方とも呼ばれ、むしろその名の方が有名です。
宋の時代の皇帝たちは医学振興に熱心で、和剤局(朝廷が運営していた薬局)で用いられる公的な処方集を作成することになりました。そこで津々浦々の医師から有益と思われる処方を集め、それらの有効性を試験し、その結果として生まれたのがこの太平恵民和剤局方です。中央政府(朝廷)が計画から編纂まで一貫して関与し、製作された世界初の医学書ともいわれています。
唐時代に生まれた中国の印刷技術は宋時代になると大きく発達し、これまで手書きで作成されていた医学書もまた出版物として広く出回るようになりました。後漢時代に生まれた傷寒論もこの頃、印刷され出版されました。太平恵民和剤局方も例外ではなく、出版後は中国だけではなく日本でも広まり盛んに用いられました。
太平恵民和剤局方には難解な理論や治療家個人の思想は除かれ、病状からシンプルに用いるべき処方が検索できる仕様になっていた点も同書が普及した理由とされています。この点は後の金元時代に生まれた文献(下記の内外傷弁惑論や脾胃論など)と大きく異なる点です。
太平恵民和剤局方に収載されている処方で今日でも用いられているものに安中散、胃風湯、藿香正気湯、香蘇散、五積散、四君子湯、四物湯、十全大補湯、升麻葛根湯、逍遥散、参蘇飲、参苓白朮散、清心蓮子飲、川芎茶調散、銭氏白朮散、蘇子降気湯、二陳湯、人参養栄湯、不換金正気散、平胃散などが挙げられます。
小児薬証直訣(しょうにやくしょうちょっけつ)
小児薬証直訣は銭乙(せんいつ)の没後、宋時代の1119年にまとめられた小児科に特化した初めて医学書です。こども達は自分自身の症状をうまく表現することができないので、充分な問診を行うことができません。そこで銭乙はこども達の顔色(面上証)や眼の状態(目内証)などを手掛かりに治療を行いました。
小児薬証直訣はそのような銭乙の独自の治療方針などが記されています。この小児薬証直訣には今日でもこども達の発育不良や体力不足などに頻用されている六味地黄丸が地黄円という名前で初めて登場することでも有名です。
内外傷弁惑論(ないがいしょうべんわくろん)と脾胃論(ひいろん)
内外傷弁惑論は1247年、脾胃論は1249年の金時代に李東垣(りとうえん)によって書かれた医学書になります。李東垣は治療において五行論の土(ど)にあたる脾(ひ)を補うこと、つまり消化器系の機能向上を重視していました。両書にはそれが通底しています。
これまでの医学書は治療を論ずるための基礎理論よりも実践的で用いやすさを重視する傾向がありました。一方で金元時代になると各流派がそれぞれの治療理論とそれを基盤とした治療法を展開するようになります。その中でも李東垣の補脾や朱丹渓(しゅたんけい)の滋陰の考え方は日本漢方(特に後世方派)にも大きな影響を与えました。
内外傷弁惑論には補中益気湯、脾胃論には半夏白朮天麻湯や清暑益気湯が載っており、これらは今日でもしばしば活躍する処方です。李東垣が創作したこれらの処方は補脾に重点が置かれ比較的、多くの生薬が少量含まれているのが特徴です。
本草鋼目(ほんぞうこうもく)
本草綱目は李時珍(りじちん)によって明の時代の1578年に完成した本草学書です。神農本草経の項目でも述べた通り「本草」とは生薬として用いられる植物・動物・鉱物の総称です。
さらに本草学は生薬単体の名称や形態を整理し、薬効や用法などを研究する学問です。この本草綱目は「元祖・本草学書」ともいえる神農本草経に匹敵する知名度とそれを凌駕する完成度を誇る本草学書です。
李時珍はそれまで存在していた本草学書には誤りや過不足が多く、それらを正す必要を感じていました。そこで膨大な文献にあたり、約25年の歳月を費やして完成したのが本草綱目です。そこには約1900種類の生薬と11000種類を超える処方がまとめられています。神農本草経に収載されている生薬が365種類だったことを考えると、本草綱目の取り扱い生薬数は単純計算でも5倍強にあたり、その凄さがわかります。
この本草綱目という後世にまで受け継がれる大著を完成させた李時珍ですが、医学を学ぶ前は官僚になることを希望して科挙(官僚登用試験)を受験しています。残念ながら結果は不合格でしたが、もし李時珍が合格していたら本草綱目は生まれていなかったことでしょう。
万病回春(まんびょうかいしゅん)
万病回春は龔廷賢(きょうていけん)によって明の時代の1587年に編纂された医学書です。この時代の日本は安土桃山時代、豊臣秀吉が天下統一を果たす3年前にあたります。万病回春は本草綱目などと並んで当時の日本医学会の主流派である後世方派に大きな影響を与えた医学書のひとつです。
日本独自の医学の黎明期を支えた後世方派の源流は明へ留学していた田代三喜(たしろさんき)、そしてその弟子である曲直瀬道三(まなせどうざん)です。万病回春は曲直瀬道三の甥であり、後継者の曲直瀬玄朔(まなせげんさく)らの世代によって盛んに研究されました。
日本の医学史に刻まれる後世方派が重要視した文献である万病回春には今日でも用いられている処方はとても多いです。その中でも代表的なものに胃苓湯、温清飲、加味温胆湯、芎帰調血湯、響声破壊笛丸、駆風解毒湯、荊芥連翹湯、啓脾湯、荊防敗毒散、香砂平胃散、香砂養胃湯、五虎湯、五淋散、滋陰降火湯、滋陰至宝湯、潤腸湯、清上防風湯、清肺湯、疎経活血湯、通導散、二朮湯、分消湯、六君子湯などが挙げられます。
万病回春の他にも龔廷賢の著作としては済世全書(さいせいぜんしょ)や寿世保元(じゅせいほげん)が挙げられます。前者には当帰飲子や補気建中湯、後者には加味解毒湯、清上蠲痛湯、竹茹温胆湯などが収載されています。
勿誤薬室方函(ふつごやくしつほうかん)と勿誤薬室方函口訣(ふつごやくしつほうかんくけつ)
勿誤薬室方函と勿誤薬室方函口訣は浅田宗伯(あさだそうはく)によって明治時代の1877年と1878年にそれぞれ書かれた医学書です。非常に難しいタイトルで憶えるだけでも大変なですが、今日の医療現場で用いられている多くの処方の運用指針となっている極めて重要な文献です。
「勿誤薬室方函」という文献名を分解してゆくと「勿誤」とは「誤る勿(なか)れ=誤った治療はするな」という戒めです。続く「薬室」はそのまま「薬局」です。この「勿誤薬室」という名は浅田宗伯の治療場の名前であり、いわばブランドネームのようなものです。「方函」は「方剤が保管されている箱(函)」という意味です。
つまり勿誤薬室方函は浅田宗伯が常々治療で用いていた処方が収載されている処方集であり、それら処方の運用方法の重要点を簡単なフレーズ(口訣)を交えて編集したものが勿誤薬室方函口訣です。
両書には浅田宗伯がゼロから創作した処方以外にも、過去の文献に収載されている処方の使用方法がわかりやすく整理されています。その中には原典からはなかなか想像もできないような、固定観念を廃した応用方法も書かれています。
有名なものにしばしば「胃酸過多症を改善する胃薬」として用いられる安中散を気血の流れが悪くなって起こる生理痛に転用したり、戦によって錯乱してしまった軍人に用いられていた安栄湯を女性のめまいやほてり感に応用しました。現在、安栄湯は婦人科系の使用方法の方がはるかに有名であり、勿誤薬室方函口訣に載っていた女神散(にょしんさん)という別名称がより定着しています。
漢方診療医典(旧題:漢方診療の実際)
漢方診療の実際は1941年(昭和16年)に大塚敬節(おおつかけいせつ)らによって書かれた医学書です。著者は当時の古方派、後世方派、そして折衷派の大家が担当しており、流派による偏りがなくバランスのとれた日本漢方の学習書に仕上がっています。後にタイトルを漢方診療医典に改めて、今日でも書店の東洋医学コーナーやAmazonでも販売されています。日本だけではなく1953年には中国、1963年には韓国でも出版されました。
主な内容は現代的な病名から頻用される処方が探せたり、口訣を交えて各処方のより詳しい解説も書かれており抵抗なく読み進められる編集となっています。その他にも漢方医学の歴史、診察時のポイントや治療方針の決め方、各生薬のはたらき、漢方用語の解説などが詰まっており、一冊で日本漢方の世界が俯瞰できます。
近年、出版されている書籍はタイトルに「漢方」と付いていても中医学の基礎理論をベースに書かれた書籍が多いです。そのような環境下でも本書はロングセラーとして生き続けている日本漢方の「入口」であり「世界地図」といえる一冊です。
本朝経験方(ほんちょうけいけんほう)
本項目は番外編となります。処方集に目を通すと出典が「本朝経験方」となっている処方がいくつもあります。しばしば誤解されるのですが、これは本朝経験方という名の文献が出典なのではなく、日本で生まれて経験的に幅広く用いられているが明確な創作者がわかっていない処方という意味です。本朝経験方は日本経験方とも表記されます。
その一方で本朝経験方という名前の文献は江戸時代に多紀元簡(たきもとやす)という折衷派の医師によって書かれてもいます。このような事実が誤解を生む一因になっているのかもしれません。
この本朝経験方に対しては厳密な定義があるわけではありません。時には大塚敬節が創作した七物降下湯や花岡青洲が生み出した十味敗毒湯のように、創作者がわかっている日本生まれの処方が本朝経験方に含まれている場合も見られます。しかしながら、多くの場合は上記で説明した通り「作者不明」を指しています。
本朝経験方の特徴としてはベースとなる処方に数種類の生薬を加えたり、2つの処方を合体(合方)させたものが多いという点が挙げられます。前者は葛根湯に辛夷と川芎を加えた葛根湯加川芎辛夷、後者は小柴胡湯に半夏厚朴湯を合方した柴朴湯などが有名です。
その他にも代表的な本朝経験方には桂枝茯苓丸加薏苡仁、五虎二陳湯(五虎湯合二陳湯)、柴陥湯(小柴胡湯合小陥胸湯)、柴蘇飲(小柴胡湯合香蘇散)、小柴胡湯加桔梗石膏、小青竜湯合麻杏甘石湯、治頭瘡一方、猪苓湯合四物湯、伯州散、茯苓飲合半夏厚朴湯、抑肝散加陳皮半夏などが挙げられます。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
中医学とは
中医学、新興勢力の台頭
日本において「漢方」の流派といえば古方派、後世方派、そして折衷派でした。近年、この中に中医学(ちゅういがく)が含まれるようになってきました。肌感覚としては1990年代頃から急速に台頭してきたと感じます。
やや復習になりますが、日本の伝統医学である漢方医学の源流は紀元前200年から紀元後200年頃に中国で生まれた黄帝内経、神農本草経、そして傷寒雑病論(傷寒論と金匱要略)にさかのぼります。継続的に中国から日本へ輸入された中国伝統医学は時代とともに「日本化」され、江戸時代頃には現在まで続く漢方医学の姿はおおむね完成されました。
その一方、中国においても中国伝統医学は姿を徐々に変え、今日では中医学と呼ばれる医学が成立しています。日本の漢方医学は明治時代に瀕死の状態に追い込まれましたが、中国伝統医学もまた西洋化の流れから存亡の危機に立たされました。
しかしながら、毛沢東の意向で中国伝統医学廃止の危機は回避され西洋医学と並び国定医学としてカリキュラムや専門の大学が整備されました。その結果として生まれたものが中医学です。
つまり、中医学と漢方医学は古代中国で同じ母親(中国伝統医学)から生まれた姉妹のような関係なのです。一方で長い年月を経て両者は似て非なるものとなってゆきました。下記ではそのような中医学の特徴をソフト面、そしてハード面から紹介してゆきます。
中医学のソフト面の特徴
中医学の大きな特徴に日本の漢方医学と比較して理論をとても重視する点が挙げられます。中国では公的に統一されたテキストをもとに学習されているので、当然といえば当然です。テキストを製作する上で理論的な矛盾や無理があるという指摘はありますが、明確に公式な見解がある点では日本の漢方医学と異なります。
これは決して日本の漢方医学に全く理論がなく、行き当たりばったりの治療を行っているという意味ではありません。あくまでも相対的な視点に立っての話です。しかしながら、江戸時代に活躍した吉益東洞(くわしくは漢方医学を築いた先人たち(3))が陰陽五行論を否定したように、漢方医学は形而上学的な基礎理論よりも実践的な治療技術を追及する傾向にあります。
その代表例が方証相対(ほうしょうそうたい)と呼ばれる日本漢方独自の診断と治療を統合したシステムです。方証相対においては病者の呈している症状(証)からダイレクトに治療に用いられる漢方薬(方剤)が決定されます。これだけではとても分かりずらいので下記で具体例をもとに解説してみます。
【ここにとある病気の人がいます。この人は急に強い寒気がして身体が震え、肩がこわばり頭痛もします。汗はあまり出てはいません。その他の目立った症状はまだありません。】
日本の漢方医学の場合、これは葛根湯証にあたるので治療には葛根湯が用いられます。なぜ葛根湯を用いるのかと問われれば「この病人は葛根湯証であるから」というトートロジーのような回答になります。傷寒論によれば上記の【急に強い悪寒がして~】以下は葛根湯を用いれば治るということ知られています。つまり、呈している症状と治療する漢方薬がすぐに結びつくのです。
漢方医学は上記のような文献上の知識に加えて、先人が積み重ねてきた経験を由来とする口訣(方剤を使用する上での重要なポイント)、体力レベルや病気の深度といった中医学と比較して簡略化された理論などを土台として方証相対を運用しているのです。
一方で中医学は趣が異なります。中医学的には【急に強い悪寒がして~】以下の諸症状からこの人は六淫の邪のなかの寒邪を受けたと考えます。そして寒の邪は消化器系症状や呼吸器系症状が無いのでまだ深くは侵入しておらず表寒・表実証(表寒実証)であると確定できます。表寒・表実証の治法は辛温解表剤であり、辛温解表剤のひとつが葛根湯です。したがって、この病者には葛根湯が用いられることになります。
上記のように、症状の診断・証の確定・治法の決定・方剤の投与を一体的に行うことを弁証論治(べんしょうろんち)と呼びます。具体例は単純なケースでしたが、もし病者が複雑な慢性病であると気・血・津液の過不足や五臓のどこに問題があるのかなど複数の理論を経て弁証論治が行われます。
見ての通り、日本漢方の場合はとてもシンプルであり実践的な治療スタイルともいえます。しかし、その途中で健康とは何か、病気の状態はどのような状態であるのか、病気を起こす原因はどのようなものであるのかといった定義付けや基礎理論がやや疎かになった面は否定できないでしょう。
この漢方医学における方証相対と中医学における弁証論治という治療シークエンスの違いは両医学のソフト面の特徴を端的に表しているといえるでしょう。
中医学のハード面の特徴
中医学においても漢方医学においても治療には植物・動物・鉱物を由来とする生薬を組み合わせた方剤を用いることは共通しています。(より厳密には両医学とも方剤以外に鍼灸なども治療に用います)一方でその使用量や種類は大きく異なります。
一般的に中医学で用いる生薬量は日本の漢方医学の2~3倍くらいが普通です。漢方医学では煎じ薬に用いる生薬の総重量は1日量が15~30gくらいの範囲に多くが収まります。一方の中医学では50gを超えるような方剤がしばしば登場します。当然、薬効成分もそれに比例して多くなっているでしょう。このような大きな差が生まれた理由は複数指摘されています。
最初の理由としては生薬の一大産地が中国とその周辺国であり、産地と消費地が近いので大量の生薬供給が容易であった点です。一方の日本の場合、一部は国産の生薬もありますが多くは輸入に頼ってきました。大昔は命がけで船を用いて輸送される場合も多かったでしょう。必然的に「節約」は避けられず、治療には必要最小限の量が用いられることになったと考えられます。
上記以外に大陸の中国人と島国の日本人では体格や体質が異なり、その結果が生薬の使用量に反映されているという説もあります。近年、西洋薬を中心に人種によって薬物を分解する能力の差、薬物代謝酵素の人種間の差があることがわかっています。基本的に単一成分の西洋薬と複数の薬効成分を含む漢方薬との比較は難しいですが、一定の説得力を持つ説といえます。
さらに生薬の加工方法の違いに着目した説もあります。中国の生薬市場には昔から偽物の生薬が多かったので、あまり細かく生薬を切断すると本物か偽物かの鑑定が困難になってしまいます。結果的に中国において生薬は鑑定が可能なレベルの大きめの裁断が一般的になりました。そうなると一定重量当たりの表面積が低下し、抽出効率もまた低下してしまうので多めの生薬が必要となったという説です。
生薬の使用量だけではなく、使用される生薬の種類が多い点も中医学のハード面の特徴といえます。諸説はありますが中医学で用いられる生薬の種類は約3000種類ともいわれています。一方の漢方医学は200~300種類が生薬専門の卸問屋から手に入れることが可能です。
この差の原因はやはり中国が生薬の一大産地であることに間違いないでしょう。膨大な生薬が身近にあれば使用できる量や種類が多くなることはとても自然な流れです。その一方でテキストには載っているけれど、実際に使用するケースは少なかったり皆無であるような生薬も少なくないでしょう。実際に中医学において用いられる方剤を構成する生薬は日本の漢方医学で頻用されるものと極端な差はない印象です。
中国が生薬の産地という理由以外に、根本的に中医学では方剤に対する捉え方が日本と大きく違っている点も大きく影響しているでしょう。漢方医学、特に日本漢方の主流派である古方派は傷寒論や金匱要略に載っている方剤の内容を堅守する傾向にあります。つまり、生薬を加えたり減らしたりすることをあまり行わないのです。
方証相対の核は方剤の特徴や運用のコツといった情報を充分把握しておくことです。患者の呈している症状とそれらの情報とを照らし合わせて、最も適している方剤が治療に用いられます。したがって、方剤はほぼ固定されているので200処方程度を構成する生薬以外のバリエーションをあまり必要としないのです。
中医学の場合、一定の決まった「型」はありますが基本的には患者に合わせて生薬をひとつひとつ選び、オリジナルの方剤を完成させてゆくことになります。治療者自身が患者に合わせて方剤を組み立ててゆくので、多くの種類の生薬が扱えた方が便利であることは言うまでもありません。結果的に中医学ではより多種類の生薬が用いられるようになったと考えられます。
中医学と日本漢方の優劣は?
上記のように中医学と日本漢方は原点を同じ中国伝統医学としながらも、時代とともに異なる進化を遂げてきました。ここで誰しも気になるのが両医学の優劣です。この点はしばしば漢方業界でも論争になる難しいテーマです。
日本において中医学派は漢方医学を「古典に拘泥して進歩を忘れている」と批判し、漢方医学派(この中にも多くの流派はありますが…)は中医学を「理論を振りかざして偉大な先人の築いた医学から乖離している」と訴えます。両者の言い分も的外れではない分、いくら議論をしても答えは出ないでしょう。
しばしば使用する生薬量も多く、生薬の種類も豊富な中医学が勝っているという論調を目にします。たしかに中医学は「完全オーダーメイド方式」といえるので、患者により適した方剤が用いられるともいえます。
その一方で漢方医学において日常的に用いられる方剤も200種類以上あります。2つの方剤を併用するなどすれば、かなりの数になるでしょう。今日、日本の漢方医学において用いられている方剤は歴史的な経過で日本人にフィットする方剤たちに収斂されている結果とも考えられます。
さらに漢方医学が歴史の中で積み重ねてきた口訣は日本人の文化社会的な背景も含めて構築されてきたものです。文化が異なれば症状の表現方法や生活習慣に密接した病因の傾向も異なります。したがって、日本に生きる日本人に対する治療経験の集積は中医学を含めた別文化で育まれた医学にはないホームアドバンテージといえます。
そういった観点から、個人的に実際の治療において中医学と漢方医学の間に大きな差はつかないのではないかと考えています。いつの時代、どの地域においても中医学や漢方医学に限らず、その道において卓越した治療者の施す治療は優れたものなのではないでしょうか。
選択画面へ戻るにはこちらへ
文・女性とこどもの漢方学術院(吉田健吾)
ページ移動
- 前のページ
- 次のページ